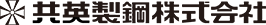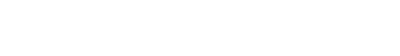- 気候変動によるここ数年の度重なる自然災害の発生や、世界各国で起こり始めた熱波など異常な気温上昇は、「地球温暖化」に対する人々の危機感を高め、企業の社会的責任としての「脱炭素社会」「エネルギーシフト」など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みに対し、社会全体の関心が強まっています。
- 日本社会は高齢化社会から人口減少社会に突入し、生産年齢人口の減少による労働力不足、需要の減退が現実化する時代が到来します。
- 世界的なエネルギー価格の上昇や円安による輸入価格の上昇に加え、日本企業の賃上げ機運が重なり、日本はあらゆる物価が上昇、日本も金利のある世界に突入し、あらゆる経済活動に金利コストを考慮した運営が必要となります。
- 「コロナパンデミック」がもたらした人間社会へのインパクトは、グローバル化や働き方に大きな影響を与え、生成AI(ChatGPTなど)の出現などでDX(デジタル・トランスフォーメーション)の動きもさらに加速してきています。
鉄スクラップを電気炉で溶解し、新たな鉄鋼製品として再生させる資源循環型事業です。ビルやマンション、橋梁や道路などの社会インフラに不可欠な鉄筋コンクリート用棒鋼(異形棒鋼)を主力製品とし、生産量において国内トップシェアを有しています。
【 強み 】
- 国内の主要需要地であり鉄スクラップ発生地でもある関東、中部、関西、中四国・九州エリアで事業を展開
①各地の販売・購買情報を活かした営業戦略のスピーディーな展開が可能
②技術情報の横展開により技術力向上のスピードアップが可能
③半製品や主力製品の鉄筋については、災害時の代替生産も可能
- 高強度鉄筋、ネジ節鉄筋などの付加価値製品を生産・販売
- 高強度せん断補強筋の母材生産から加工までをグループ内で完結
- 低品位の鉄スクラップから基準を満たす鉄鋼製品を安定的に生産できる操業技術
【 機会 】
- 地球規模のカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーの要請による電炉事業の地位向上
- 社会インフラの更新需要により、鉄筋の需要は一定程度継続
- 豊富な原材料(鉄スクラップ)で安価に生産できる鉄筋は、建設用鋼材として代替品が少ないため、需要は継続
【 脅威・課題 】
- 需要は中長期的に縮小
- CO2排出量削減の流れによる鉄スクラップ価格の上昇、調達困難の可能性
- 新たな建築工法への対応
- 生産年齢人口の減少に伴う労働力確保の困難さ
- 工場設備の老朽化
当社は、2024年3月31日に関東スチールを合併、関東事業所とし、国内4事業所体制となりました。
その目的は、①BCP対応:4事業所連携による製品の安定的な供給体制の構築、②最大需要地である関東圏におけるプレゼンス向上、の2つにあります。
国内4事業所体制の盤石化のため、各事業所間の連携強化をさらに進め、最大需要地である関東圏におけるプレゼンスの向上を図ります。また、名古屋事業所で製造する高強度鉄筋などの付加価値製品の拡販にも努めます。原材料調達の多様化などの川上戦略として、グループ会社である共英マテリアルを軸としたサテライトヤード設置などによりスクラップ調達機能を強化します。生産企画部にエンジニアリング部門を新設し、国内外の製造拠点の恒常的な安全・安定操業を実現します。さらに、「NeXuS 2023」に引き続き、製鋼工場に自動測温装置・自動分析装置、圧延工場にサンプリングロボットを導入するなど、労働力不足の課題に対応するため、合理化や効率化を進めます。
2024年問題(建設・物流現場の人手不足や働き方改革)、猛暑による工期の遅延・長期化により国内需要が減退するなか、売買価格差(製品価格と原材料価格の差異)を維持しながら、シェア18%以上を確保しました。
愛知県知多市に鉄スクラップ集荷のサテライトヤードを確保したほか、スクラップ事業を営む(株)東洋商事を買収し、鉄スクラップ調達力を強化しました。
国内外の製造拠点の恒常的な安全・安定かつ効率的な操業に資するため、エンジニアリング室を設置し、専門チームによる設備診断・操業診断等を実行しました。
ブランド戦略として「エシカルスチール」をスタート。資源循環型社会に貢献する当社事業のイメージアップを図り出荷量増加につなげます。