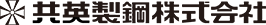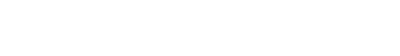- 日本における廃棄物処理・資源有効利用分野の市場規模は今後も拡大するものの、当社グループの環境リサイクル事業の関連マーケットである「廃棄物処理・リサイクル」は廃棄物発生量の抑制により横ばいで推移すると予想されます。
- 廃棄物排出元の環境への意識の高まりにより、マテリアルリサイクルなど、より高度なリサイクル方法が求められるなか、廃棄物発生量抑制に向け3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みも各方面で進められています。一方で、簡易で安価な焼却炉の台頭や新たなリサイクル技術の開発により、電気炉による溶融処理に対する競合も出現しています。
- リチウムイオン電池などの新素材は、現時点ではリサイクルは困難であり、コスト面からも当面は確実な処理(廃棄)が必要とされています。
1980 年代後半、使用済み注射針の不法投棄という社会問題をきっかけに、電気炉で鉄スクラップを溶解する際に発生する数千度の熱を有効利用しようという発想から、当社が処理技術を開発し、ビジネスモデルを確立した事業です。電気炉による無害化溶融処理のパイオニアが手がける安全・確実な処理として多くの企業や自治体から信頼を得ており、電気炉による産業廃棄物処理において5 割以上のシェアを有しています。
その他の大型処理設備としては、山口事業所で稼働するガス化溶融炉があり、自動車のシュレッダーダストなどを溶融・ガス化処理し、金属類を溶融メタルとして回収・リサイクルしています。また、その処理において生成されたガスは、燃料として同事業所内の加熱炉で利用しています。
【 強み 】
- 電気炉で発生する数千度の熱により、廃棄物を完全無害化処理、廃棄物中の鉄成分は鉄鋼製品の一部としてリサイクル
- 鉄鋼の品質を維持しつつ電気炉で廃棄物処理を行う技術・ノウハウを自社で確立
- アスベスト、車載用リチウムイオン電池などの難処理廃棄物も処理可能
- ガス化溶融炉による廃棄物処理事業も展開
【 機会 】
- 難処理廃棄物の処理ニーズは今後も拡大
- 資源有効利用市場の拡大
- 環境関連企業とアライアンスを組むことで、業容の幅を広げやすい(相互に不得意な処理廃棄物を相互に補完することで収益機会の創出)
- リサイクル関連法の規制強化による廃棄物処理市場の拡大
【 脅威・課題 】
- 簡易で安価な焼却炉の台頭による競合他社の増加
- リサイクル技術の進展による難処理廃棄物のマテリアルリサイクルへの移行
- 鉄鋼生産工程の中で処理を行うため、電気炉の溶融処理能力に制約あり
当社は、山口事業所におけるメスキュード事業の開始以来35年を超える歴史を持つ環境リサイクル事業のパイオニアです。廃棄物処理が単なる処理事業者としての位置づけから、社会にとってエシカルでエッセンシャルな事業者として評価される時代に変化してきていることを踏まえ、当社では、鉄づくりと医療廃棄物や産業廃棄物処理を一体として行ってきた歴史を見える化し、事業の独自性をブランド化することとしました。電気炉溶融処理の強みを活かしつつ、資源リサイクル技術の開発にも注力し、社会の環境意識の高まりに伴う様々な廃棄物リサイクルへのニーズに応え、より品質の高い資源循環型ビジネスを目指します。
当社はこれまで鉄づくりと医療廃棄物・産業廃棄物処理を一体として行ってきた歴史があり、「電炉溶融処理のパイオニア」として他社にはない独自性をブランド化、見える化し、幅広く浸透・周知を図ることで、業績の立て直しに努めていきます。また電炉溶融処理のみならず他社との連携による「廃棄物処理のワンストップ体制」の強化も図ります。鉄づくりと廃棄物処理を一体として行う「資源循環型事業」をさらに極めることで、さらなる成長を目指します。
2025年6月に光和精鉱株式会社との業務提携を締結しました。これにより、当社の電気炉・ガス化溶融炉の活用および同社の塩化揮発法を用いたリサイクル技術の融合による市場の難処理廃棄物の相互補完や、双方のネットワークを活用した廃棄物の集荷量の拡大およびサーキュラーエコノミーに向けた技術開発を実施し、資源循環型社会の実現に貢献していきます。
また、廃棄物を処理しながら製造した鋼材を、「エシカルスチール」としてブランド化し、当社の環境リサイクル事業の社会的価値の認知度向上を図りました。